Medical Information Network for Divers Education and Research
一般ダイバーの方は、“医師というものは全ての疾患の勉強をしているはずなので、当然減圧症についても大学で
講義を受け、その病態については精通している”と思っている方が多く存在しているようである。
しかし、これは大きな誤りである。
あえて言えば、減圧症は衛生学で講義されておかしくない内容であるが、海外を含めた潜水に関連した医学会にて、
発表されたり参加されている衛生学の教官を見かけることは少ない。よって、日本の衛生学の教官で減圧症患者の
診療経験がある医師は極少数であると思われ、当然医学生に対する講義が行なわれている可能性はほとんどないと
いうのが現実と思われる(このことはもちろん何も問題が存在しているわけではない)。
当然、私の学生時代にも減圧症の講義は全くなく、医師になってからも東京医科歯科大で減圧症患者の診療に当た
る前は減圧症患者を診た事はなかった。当然、その発症機序についてもあまり正確な知識を持ち合わせていなかった。
現状においては、減圧症を診療する方法で日本の医学界全体に普及しているようなものは存在せず、診療に当たる
各医師が自分の考えのもとに診察を行なっているというのが現実であろう。
現在の東京医科歯科大の減圧症診療が確立されたのは、実は私が診療を行い始めてからのことである。私も減圧症
の診療を始めた当初はなにを診たらよいのかさえ判らずにいた。減圧症による障害は基本的には神経と関節の障害が
メインである。よって、整形外科医である私の専門領域と一致していたため、医科歯科大で以前より行なわれていた診
療方法を基に、整形外科的な所見も併せてとるようになっていった。
東京医科歯科大での減圧症診療の基本は、減圧症に特有なものは少なく、一般的な診療方法である、
問診・診察・治療から成り立っている。
減圧症でいう問診とは、潜水からどのくらい経過して発症したか、航空機搭乗や高所移動との関係はどうか、潜水プ
ロファイルはどのようなものであったか、潜水中に急浮上などのエピソードがあったかという点が重要である。
しかし、潜水プロファイルは潜水深度が浅くとも、潜水時間が短くとも減圧症と同様な障害を生ずる動脈ガス塞栓を
否定することが出来ないため、これだけで潜水障害の存在を否定することはしないようにしている。
潜水から減圧症が発症するまでの潜時は、DANアメリカなどは統計上99%は24時間以内に発症しているとしてい
る。確かに、減圧症のメカニズムを考えると、潜水終了後数時間以内に発症しているはずであり、この結果は妥当と
考えることはできる。しかし、私が医科歯科大で詳細な神経学的所見をとるようになると、何も訴えのない部位に障害
がある患者が多いことに気づいた。つまり、発症しても気がつかないことが意外と少なくなく、それが不定愁訴に繋がっ
ていたことがわかってきたのである。
これは、日本高気圧環境医学会での発表内容であるが、四肢と体幹部を5つに区分けして、自覚症状のある区画と
実際に神経障害が見つかった区画を比較して、その一致度を表したものである(図1)。多くの患者に、自覚障害のない
神経学的異常所見が存在していることがわかる。
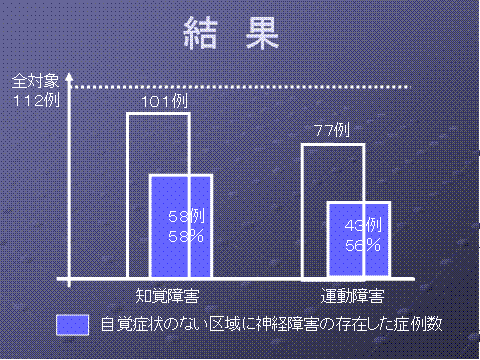
図1
このような、自覚症状のない減圧症障害が存在していることがわかってからは、減圧症症状を発症した時間が潜水
より長時間を経過していたとしても、気づかずにいた可能性も高いと考えて、発症時間だけで減圧症を否定することは
しないようにしている。
診察においては、ほぼ全員(潜水前から愁訴があったなど明確に減圧生を否定できる場合以外)に愁訴の有無に関
わらず全身の知覚所見と筋力所見はとるようにしている。前記のように、愁訴のない障害が多く存在するためである。
さらに、めまいなど知覚や運動障害以外の愁訴で来院した場合も、めまいに関係する所見で減圧生特有のものは少な
いため、これらら知覚や運動障害の合併にてより強く減圧生の存在を疑うことができるようになるので、知覚と運動の所
見はとるようにしている。
減圧症に特異的な神経学的所見は、知覚障害と運動障害に解離が高頻度で認められる点である。このことは、私が
以前Undersea Heperbaric Medicineに投稿した論文に記載されているため、興味のある方は目をとおして頂けると幸い
である(図2)。神経学的な所見をとって、そこに神経学的な解離現象を認めた場合は、減圧症の可能性が極めて高い
と判断して、さらに診療を続けることになる。
しかし、これらの診察をいかに慎重に多く行なっても、減圧症の確定診断には至らない。最終的には、再圧治療を行い、
それによる反応の有無を含めて診断する必要性があるからである。具体的には、前記の神経学的所見が治療の前後
でどのように変化するか、治療中にしびれや疼痛の増強や変化が見られるかなどを確認して、減圧症を診断する必要
性がある。
これは、減圧症の専門医にとってはあまりにも当たりまえのことであり、潜水医学の成書においても記載されているこ
とは少ないが、海外でのUndersea Hyperbaric Medicineなどの潜水医学の学会では当然のように話されていることであ
り、診断においては不可欠なものと考えている。
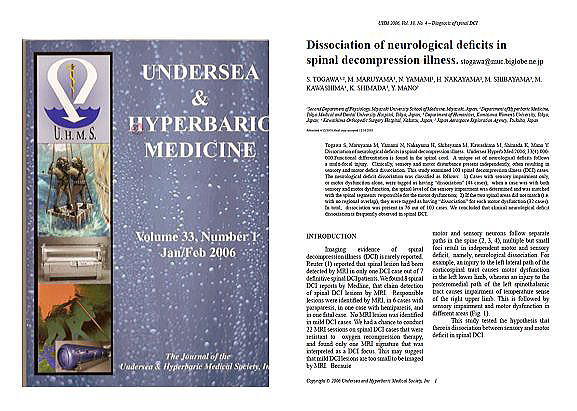
図2
しかし、このような当院の診療方法が正しいのかは、判断が難しいところである。以前は、減圧症の治療は一刻の
猶予もないため、チャンバーの中に減圧症患者と一緒に医師が入り、治療準備を進めながら診察を行なうものとされ
てきた。現在でも、そのように信じている医師は相当存在している。このような医師から見ると、当医科歯科大の診療
方法は時間がかかりすぎる点より望ましい減圧症患者の診療方法とは捉えられない可能性が高い。
しかし、医科歯科大というダイビングポイントから大きく離れた場所の施設に来院する減圧症患者は、大部分は軽症
で更に発症から数日を経過していることが多い。このような患者の診療には緊急性があるという理由は存在していない
のは明白であり、当方では上記のような診療を継続して行なっている。
さらに、最近DANアメリカで作製された、減圧症の診療マニュアルにも、当方の施設で行なっているのとほぼ同様
な医学所見のとり方が記載されていることが確認できる。よって、現時点では当施設の診療法は世界に通用する診察
方法なのではないかと考えている。
その他、減圧症では神経学的な異常を伴わない症状も出現する。その一つは心肺系の異常を伴う減圧症である。
当院にも、潜水後の呼吸困難を愁訴に来院する患者は多く存在する。心肺呼吸器系減圧症で最も多いのは、
チョークスといわれる病態である。全身の静脈で生じた気泡(ある程度の窒素負荷がかかる潜水では、高率に静脈に
気泡が発生する)は、心臓に戻った後、肺の毛細血管を必ず通過する。この際、毛細血管より気泡は大きいため肺を
通過することはできなく、毛細血管は詰まってしまう。
そのため、そのような毛細血管では動脈内への酸素の受け取りが出来なくなるために(ガス交換ができない)、血液中
の酸素分圧が低下する。さらに、肺を血液が通過できなくなることより、循環血液量が減少して血圧も低下して生命的に
危険な状態に陥る可能性が高いと考えられている。医科歯科大では、このような病態を想定して、呼吸苦のある患者に
対して、動脈中の酸素分圧を測定することで、チョークスが生じているかを診断している。
すると、大変興味深い結果が観察されている。それは、呼吸苦があるのに関わらず、逆に動脈中の酸素量が増加し
ているケースが多々みられるというものであった。そこで、このような患者の呼吸苦を自覚する原因を探ったところ、この
ようなケースでは胸部の神経学的な異常を高率に伴っていることが判ってきた。
つまり、胸部の知覚異常が、呼吸機能に異常がないにも関わらず呼吸しづらいという自覚を招き、さらに過呼吸状態
になっているということである。胸部の知覚異常も減圧症であり、再圧治療を遂行するので問題はないが、潜水の障害
に関して診療する場合は、全身の知覚や運動に関する神経学的な所見をとることは非常に意義あることと考えている。
当然、潜水後に生じた呼吸苦が全てチョークスと捉えることは誤っていると考えている。
その他減圧症の障害は、めまいや難聴などの耳鼻科的障害、頭痛や嘔気、視野障害などの脳神経的障害など多岐
にわたる。もし、発症からの時間経過が短く早急に治療するべきと判断された場合は、各障害部位に応じた専門医へ
のコンサルトする時間がないため、我々の行なえる範囲で障害に応じた所見をとって、客観的な障害の程度の評価を
おこなっている。
しかし、発症よりすでに数日を経過している場合には、可能な範囲で専門医の受診を勧めている。例えば、めまい、
難聴では耳鼻科医による聴力検査や眼振といっためまいの評価には不可欠な所見の有無や程度などの評価が必要と
なってくる。
我々の行なう筋力や知覚の検査や、前記の耳鼻科的な聴力や眼振の検査などの所見は、障害の客観的な存在の
証明になるばかりでなく、治療効果の客観的な指標ともなる。患者が自覚的には治ったと感じても障害が残存している
ことは多く、その時点で診療を中断してしまうとその障害が遺残してしまうことが考えられるからである。
以上、医科歯科大にて行なわれている、潜水後の障害に関する診療内容を簡単に述べさせていただいた。
このような診療は、医科歯科大高気圧治療部が日本で数少ない減圧症専門の医療機関であるという自覚のうえで行
なわれていることである。よって、このような診療を他の医療機関に求めることは不適当であると思われる。減圧症診療
には、時間的な制約がある。そのため、診察より治療を優先しなくてはならい。
そのため、最も重要なことは減圧症発生時に可能な範囲で近隣の施設にて再圧治療を行なってもらうことである。
その際には、以上のような診療を求めることは事実上不可能であり、さらにそのような減圧症に関する見識を要求して
はならないと考える。
しばし、ダイバーが医療機関でトラブルを起こしていることを耳にするが、医療側がこのような減圧症診療の知識を
備えることは不可能なのであることをよく理解して頂き、医療側と対応していただきたいと考えている。
速やかに、再圧治療を施行していただき、それでも不安や障害が残存した時に、医科歯科大の専門的な診療を受け
て頂くのが、現実的にもっともよい方法と考えている。
減圧症は、極めて特殊な疾患であり、その病態を正確に把握している医師はほとんど存在していない。
そのことを念頭に置きながら、ダイバー自身も減圧症の知識を持ち、かつ現実的に最良な医療を受けられるように考
えていかなければならない。